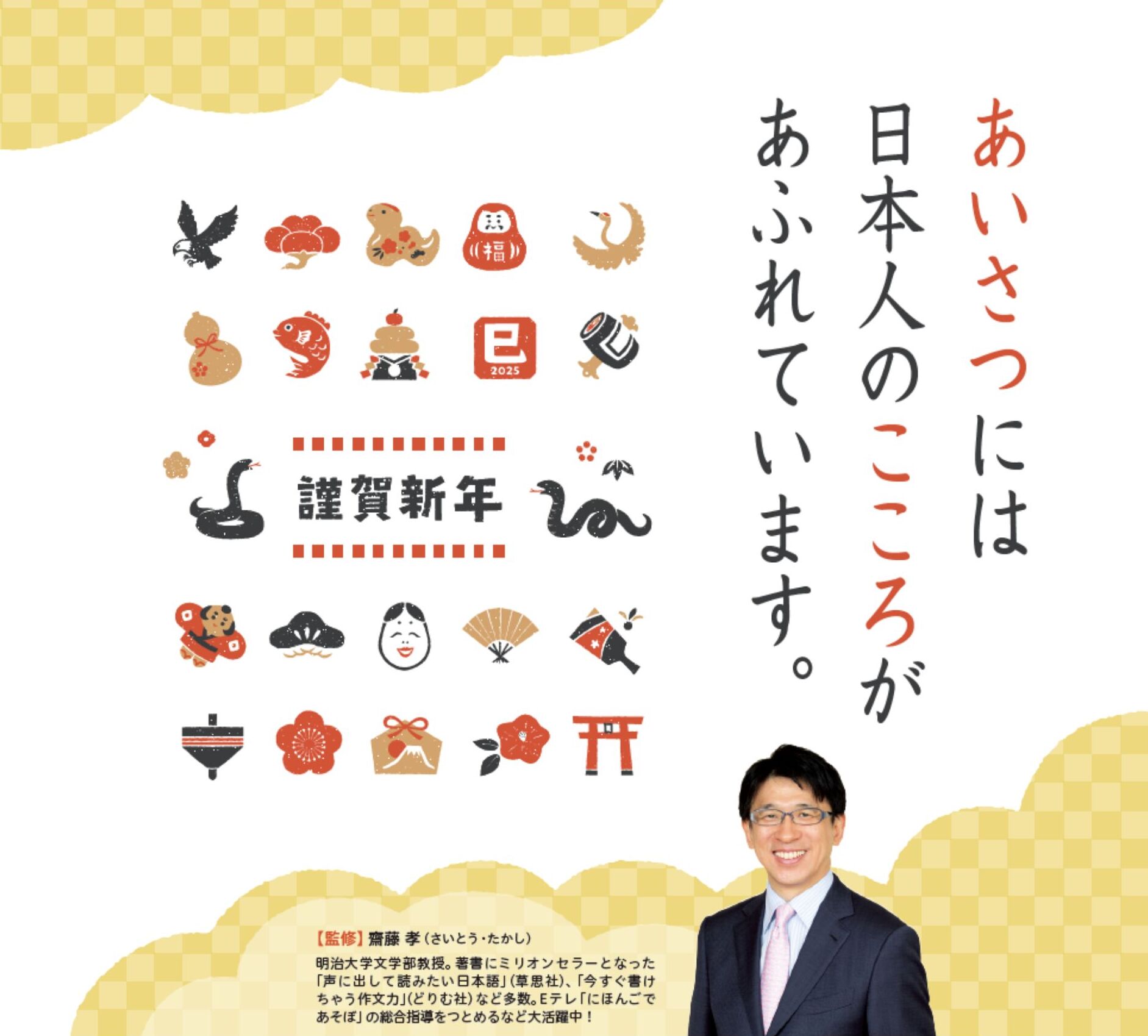HOME > 齋藤孝先生インタビュー > Vol.66 あいさつには日本人のこころがあふれています。
Vol.66 あいさつには日本人のこころがあふれています。
国の安泰を願う「言霊」
「初春(しょしゅん)の令月(れいげつ)にして、気淑(よ)く風和(やはら)ぎ、梅は鏡前(きょうぜん)の粉(こ)を披(ひら)く、蘭は珮後(はいご)の香(かう)を薫(かをら)す」
現代語に訳すと、「時は良き新春、外の空気は気持ち良く、風はやわらかに、梅は美女の鏡の前の白粉のように白く咲き、蘭は身を飾る香のようなかおりを漂わせている」という意味になるでしょうか。
新春らしいすがすがしい感じがしますよね。
令和になって6回目の新年が始まります。先の一文は「令和」の文字が取られた万葉集の序文の一部です。
思い出されたでしょうか。万葉集について少し復習すると
・ 二十巻から成る長大な書物で、四五〇〇首もの和歌が収録されている
・ 収録された和歌は、短歌だけではない
・ 和歌はすべて「万葉仮名」という漢字で書かれている
・ 天皇から庶民まで、さまざまな階層の人の歌が差別なく集められている
日本の古典です。
令和になったのをきっかけに万葉集を手にとった人は少なくないと思いますが、その一方で機会を逃してしまった人は、これを機にぜひ、手にとってみてください。そしてその際に少し意識して、万葉集から「言霊」として言葉を受け取ってほしいと思います。
山上憶良の歌に「言霊」が出てきます。
倭(やまと)の国は 皇神(すめがみ)の厳(いつく)しき国 言霊(ことだま)の 幸(さき)はふ国と 語り継ぎ 言ひ継がひけり
五・八九四 山上臣(おみ)億良
言葉は霊であるという認識が、万葉人の根底にあります。言霊を信じた万葉人と心を同じくして、万葉の歌を読んでもらいたいと思います。
万葉集が国家プロジェクトであったのは、言霊の力で国を治めるという強力な意志があったからです。庶民を含む、心の歌が良い国をつくることにつながるという思いがあったはずです。
膨大な歌を集めたのは、為政者の徳を養うためであり、言葉で国を治めるためです。万葉集は日本の礎を目指したものだったのです。
歌を一つつくることは、覚悟として、仏像を一つ彫ることと同じであり、万葉集は大仏(同じ奈良時代)をつくるのと同じことだったのです。
国の安泰を願う壮大な理想、そして一人ひとりの思いをくむ優しさ。それを支えるのが言霊信仰だったのです。
「日本人」というアイデンティティ
日本の伝統的な習慣やたしなみを考えるときに、キーワードになるのは「日本人」というアイデンティティです。アイデンティティとは、自己の存在証明です。自分は何者であるのかを認識すること、あるいは心のよりどころと言ってもいいでしょう。それが、生きていくうえでの張り合いとなります。誰もが、いろいろなアイデンティティを持つことによって、自分自身の心の軸をつくっています。もし、自分のアイデンティティがわからなかったら、心の軸が持てずに“生きる張り”も失われてしまうでしょう。自分の持っているアイデンティティを一つひとつ確認しながら生きていくことで心がしっかりします。
私たちは日本人であることを認識し、心のよりどころにしています。
では、私たちが持っている「日本人」というアイデンティティとは何か……。私は、「日本人」というアイデンティティは「日本語」とセットであると考えます。言霊の力が込められた日本語でコミュニケーションをとるからこそ、日本人という共通項を認識できるからです。
日本語がなくなると日本人のアイデンティティは大きく揺らぎます。
それは、「日本語」が私たちの感性のおおもとになっているということです。
日本人がこれまで培ってきたならわしや、心遣い、あいさつ、人づきあいのマナーなどの行動習慣があります。それらは日本語でのコミュニケーションを経て共通理解を得ることができます。まさに“日本語なくして日本人なし”です。
日本語に限らず、言語とアイデンティティは強い結びつきがあります。たとえばアイヌ語は、アイヌの人のアイデンティティの核心であり、アイヌ的世界観そのものです。
日本固有の文化・精神を心身に定着させる
私たち日本人が日々の暮らしのなかで培ってきたたしなみ、人と人との心をつなぐあいさつの言葉や作法は、いずれも、先人から受け継ぎ、醸成してきた“日本人らしさ”です。
近年はインターネットの発達によって世界中が一瞬にしてつながります。これだけ世界がつながると、固有の文化を持っていることが強みになります。固有の文化がなくなり、世界中が全部同じようになると、まったく面白みのない世の中になるでしょう。
さまざまな“日本人らしさ”は、世界に誇れる日本固有の文化です。ところが現代の日本社会においては、ライフスタイルや社会環境の変化により、こうした日本人らしい習慣の多くが忘れられつつあります。それ自体は知っていても意味や由来となるとぼんやりとしかわからないことが大半ではないでしょうか。なぜ、「いただきます」「ごちそうさま」というのか。
正月という、日本人にとってその年神様を家族で揃ってお迎えするという大切な日に、古来からつながる心遣い、相手の健康状態を気遣ったり、相手への感謝の気持ちが込められたあいさつの言葉の意味を知ることでこれまで以上に心豊かな新年を迎えられるでしょう。
「あけましておめでとうございます」日本の独特な感性を改めて感じ、個々の「日本人」というアイデンティティを確かなものにしてはいかがでしょうか。その言葉の意味を理解し、くり返し実践することで習慣が身につくのです。先人から受け継いだ心を笑顔で伝えていきたいものです。
みなさまにとって幸多き一年でありますよう、心よりお祈り申し上げます。
vol.66 ブンブンどりむ 保護者向け情報誌「ぱぁとなぁ」2025年1月号掲載