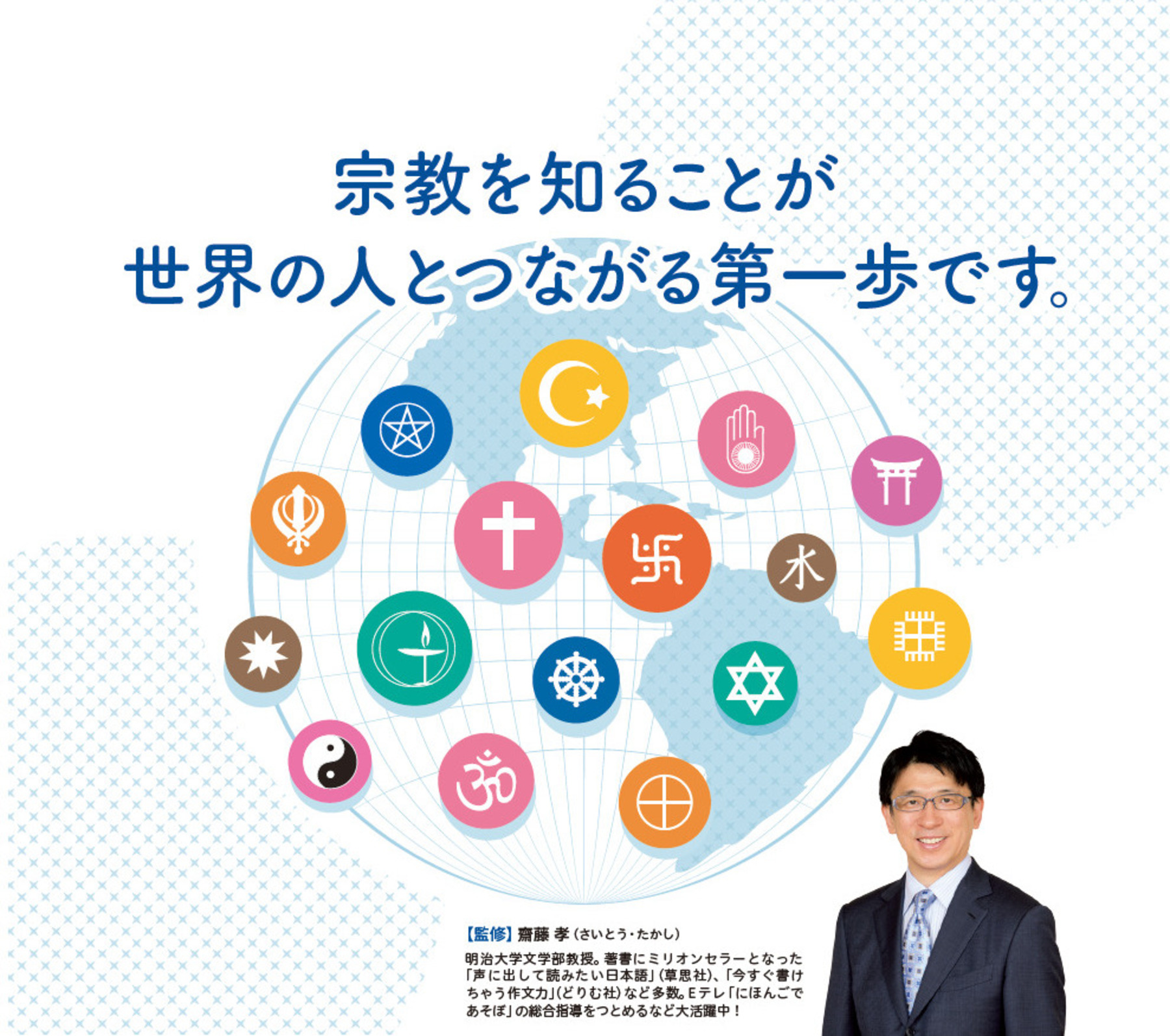HOME > 齋藤孝先生インタビュー > Vol.67 宗教を知ることが世界の人とつながる第一歩です。
Vol.67 宗教を知ることが世界の人とつながる第一歩です。
人はなぜ宗教を求めるのか
21世紀は科学の時代になる。宗教を信じる人、少なくとも本気で宗教を信じる人は激減し、科学技術万能の時代になる。――20世紀の半ばには、世界の多くの人がこのように考えていたのではないでしょうか。未来は宗教が廃れ、科学技術こそが信ずべき対象になるだろうと。
確かに20世紀も、すでに四半世紀が過ぎた21世紀も、科学技術は世界を覆い、私たち人類にさまざまな恩恵を与えてくれています。しかし、宗教を信じる人が減り、宗教が歴史の世界のみの話になったかというと、決してそうではありません。そのことは、日々の報道に接していれば、誰もが実感できるはずです。それこそ、イスラム組織に関するニュースは、毎日のように伝えられています。
もちろん、過激な話だけではありません。自分の信じる宗教に帰依し、祈り、心静かに穏やかに、神仏とともに過ごしている人は、今も世界に大勢います。21世紀の今も、宗教の影響力は依然、大きいままなのです。
「不安」が宗教を生み出した
それにしても、宗教はどうしてこれほどまでに人を惹きつけるのでしょうか。宗教の根源的な魅力はいったい何なのでしょうか。
人が宗教に惹きつけられるのには、いくつかの理由があると思います。その一つは「不安」です。これが宗教を生み出したといってもよいでしょう。
「死ぬのなんか、怖くないし、不安でもないよ」と言う人もいるかもしれませんが、多くの人にとって「死」は不安だし、怖いものであるはずです。自分の死だけではなく、肉親や愛する人の死も不安だし、そうした死に接すれば、悲しみに包まれることにもなります。動物は人ほど死を恐れません。
宗教は人間のこの特性にグッと入り込んできました。死ぬのは怖い、恐ろしい。この不安や恐怖に対して「来世がある」と言ってもらうことで、心はどこか安らぎます。あるいは「魂は死なない、永遠である」と言われると、救われる気がしてきます。
これがもし仮に、人間が不死の生物で、老いも病も知らず、年齢を重ねるごとにますます元気になっていくような存在ならば、宗教は生まれなかったかもしれません。老いや病や死があり、悔いや恨みや怒りがあり、つらく悲しいことがあるからこそ、宗教は生まれたのでしょう。
宗教の役割
不安のほかに、宗教を支えている大きな要素として、「アイデンティティ」もあります。自分が何者であるのかを考える際には、自分が属している、あるいは属していた集団を考えることが大切です。
自分の存在を見いだしたり、証明したりできると、人は安心します。逆にいうと、アイデンティティがないと、とても不安になります。ある意味、宗教はこの不安を数千年以上も前から解決していました。
ユダヤ教徒であれば、『旧約聖書』のすみずみまで知っている、イスラム教徒であれば、『コーラン』のすみずみまで知っている、こうしたことは同じ場所に所属し、同じものを信じていればこその共通の大きな財産です。
ユダヤ教徒もイスラム教徒も、豚肉を食べません。こうした日常の取り決めや習慣の共有もアイデンティティを育みます。
「豚肉なんて、食べないよね」
「当たり前だよ。食べるわけないじゃないか」
こうした意識が共有されていくわけです。
また、宗教には、共同体のルールとして機能していた、あるいは今も機能している側面も当然あります。
近代国家では整備された法律にのっとって、社会は営まれています。しかし、近代法が発達する前には、世界的に宗教が世の中の秩序を保っている部分が多分にありました。「法律の代わりとしての宗教」があったわけです。
ただし、根本の発想は違っています。近代的な発想では、国なり地域なりのルールに反する行為をしたから罰を与えると考えますが、宗教の場合、神の命令に背いたために罰する、といった考え方をします。
神、少なくとも一神教における神は絶対的な存在です。神聖であり、比類なき権威を持っています。誰もがひれ伏す存在である神を設定し、神のもとに共同体をつくり、それをみんなが守る。そのルールを破れば、神に背いた者として処罰される。そういう社会がかつては世界の各地で営まれていました。その典型であるのが、イスラム世界です。イスラム法が確立していて、生活のすみずみまで規定しています。そして、こうした社会のあり方は、今も連綿と継続されています。
21世紀の日本人の課題
2001年の9・11事件の衝撃は、21世紀が「宗教間の対立の克服」を課題としていくことを、私たちに予感させました。
2023年、イスラム組織ハマスがイスラエルに大規模な襲撃を仕掛け、1年余。激しい攻撃はいまも続いています。
今、私たち日本人にとってまず必要なことは何か。それは、「理解」です。
そもそも「世界で最も解決が困難」といわれてきたパレスチナ問題とは何なのか。
なぜイスラエルとパレスチナは凄惨な対立の歴史をくり返してきたのか。世界の宗教の歴史の基本を「理解」することは、国際社会を生き抜く私たちにとって必須のことになったのです。
私たち日本人は、深刻な宗教対立の世界を日々生きているわけではありません。宗教の違いよりも、日本という共通の基盤をもとに安定した社会を形成してきました。外から見れば、「日本教」ともいうべき独特の慣習と空気を共有しているともいえます。
そんな状況が、「宗教音痴」ともいわれる状態を生んできたわけですが、これからの世界は「宗教理解」を抜きでは立ち行きません。世界の宗教の歴史と本質を学んでいくと、「人間とは何か」がわかってきます。私自身、宗教について学ぶことで、人間観・歴史観を深めることができた喜びを感じています。
改めて世界の宗教を眺めることで、私が感じた「世界を知り、世界とつながる喜び」を共に感じてもらえたら、うれしく思います。
vol.67 ブンブンどりむ 保護者向け情報誌「ぱぁとなぁ」2025年2月号掲載